 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】人も妖怪も化粧で変わる?「つらがわり」と百鬼夜行絵巻の妖怪
2016年9月4日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 ぱっと見 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】モデルは豊臣秀吉か?苦労人の「かたづ家来」
2016年9月3日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」 をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。
『妖 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】「ヒキコウモリ」は年齢を重ねると「野鉄砲」になる?
2016年9月1日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」 をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。
「ヒ … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】実は同じ妖怪がモデルになっている?妖怪「犬神」と「ズキュキュン太」
2016年8月31日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 …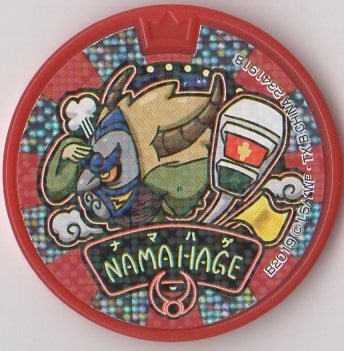 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】今も昔も子供を見守り続ける妖怪「なまはげ」
2016年8月30日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 妖怪ウォ … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】汚いものをなめるのには理由があった?風呂場と「あかなめ」の関係
2016年8月29日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 古典妖怪 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】河童も頭が上がらない?中国原産の「水虎」
2016年8月28日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 古典妖怪 … 妖怪
妖怪【実話 怖い話】 山を行くもの
2016年8月27日 ATLASEDITOR ATLAS
筆者の故郷である四国には、山林業に従事する人が大勢いる。山で働く彼らは、時に奇妙な出来事に遭遇する事があるという。 「それも含めて山なんですよ」 彼らにとって、山の不思 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】妖怪「びきゃく」は男らしい妖怪だった!?
2016年8月27日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」 をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。
た … 妖怪
妖怪【実話 怖い話】黄泉に誘う黒いモノ (後編)
2016年8月26日 ATLASEDITOR ATLAS
≪前編より続く≫ まるで、死に便乗して姿を現す死神のように。黒い物体と人の死がまるでセットのように、何度も彼の前で展開された。 「あいつは、死神だ」 後藤さんは黒 … 妖怪
妖怪【実話 怖い話】黄泉に誘う黒いモノ (前編)
2016年8月26日 ATLASEDITOR ATLAS
後藤さん(仮名)の実家は北陸の某所にある。江戸期から続く名門で、その屋敷は築百年を越えていた。庭も大きく、その屋敷は付近でも豪邸と呼ばれていた。 しかし、昭和五十年代の石油シ … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】白粉で妖怪は変身する!?「しわくちゃん」「老いらん」と「白粉婆」
2016年8月24日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」 をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説し ていくコーナーです。 若い … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】セミの妖怪はいない?「セミまる」の元ネタは山田風太郎か?
2016年8月23日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」 をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 プリチ … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】骨になっても綺麗でいたい「しゃれこ婦人」と「骨女」
2016年8月22日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」 をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説し ていくコーナーです。 プリ … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】普通の人が妖怪に!?古典妖怪の代表格「ろくろ首」
2016年8月21日 ATLASEDITOR ATLAS
妖怪ウォッチ2にて古典妖怪の一人として登場したろくろ首は、「女性の妖怪」と聞いて誰もが思い浮かべる妖怪の一人(?)だろう。 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】実は元ネタに忠実だった!妖怪サイボーグ「からくりベンケイ」とは?
2016年8月20日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 「ベンケ … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】元ネタはただのダジャレか? トオセンボン
2016年8月19日 ATLASEDITOR ATLAS
ゲーム第1作目から登場したトオセンボン。理由はわからないが、道行く人を通せんぼする妖怪。体にトゲが生えており、魚のような尻尾も生えていること … 妖怪
妖怪【怪談実話】姑獲鳥(うぶめ)が訪問する家 奇妙な足音(その2)
2016年8月19日 ATLASEDITOR ATLAS
(その1)から続く 「だから、山口さんに鳥の妖怪がいるのかって聞きたかったんですよ」 私は興奮を抑え切れなかった。鳥のような姿 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】今となっては珍しい妖怪?「ウ魔」と馬に憑依する妖怪「頽馬」
2016年8月19日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」 をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 「ウ魔 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】目撃すると精神異常に!?恐怖の都市伝説がモデルになった妖怪「のらりくらり」
2016年8月18日 ATLASEDITOR ATLAS
『妖怪ウォッチ2』から新登場したブキミー族の「のらりくらり」はその名の通りのらりくらりと身をかわす妖怪で、どれだけ文句を言われても全く応えな … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】かわいい妖怪のお姫様「百鬼姫」は兵庫出身だった!?巨大化してコウモリを操る特殊能力も?
2016年8月17日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】「妖怪の総大将」の姿は作られたもの!?「最凶の妖怪」ヤミまろとぬらりひょんの関係
2016年8月16日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 妖怪大辞 … 妖怪
妖怪【実話 怖い話】四国 その2 おっぱしょ石
2016年8月16日 ATLASEDITOR ATLAS
「狸=イヌガミ」という考え方だが、気になる事件が近年もあった。2001年筆者は徳島郷土史家である多喜田氏に連絡をとった。「おっぱしょ石」の背後にある穴蔵についてである。 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】百鬼夜行絵巻の最後に現れた、最強の妖怪!?「ゲンマ将軍」と「黄泉ゲンスイ」
2016年8月15日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 カブトと … 妖怪
妖怪妖怪ウォッチは実在した!?妖怪を見つける方法・妖怪を呼び出せる道具とは
2016年8月15日 ATLASEDITOR ATLAS
レンズで妖怪を探すことも出来て、ともだちになった妖怪を召還することも出来る便利な道具の妖怪ウォッチ。 現実には妖怪ウォッチのような道具 … 妖怪
妖怪【実話 怖い話】四国 その1 憑き物
2016年8月15日 ATLASEDITOR ATLAS
四国と中国地方の一部に伝承されている犬神は今も実在し、それを自在に使いこなす一族は今も存在するという。果たして、21世紀の現在、犬神は存在するのであろうか。 筆者・山口敏太郎 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】ヤモリなのにカエルの親戚とはこれいかに?妖怪「大やもり」とイモリの関係
2016年8月14日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 妖怪ウォ … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】本家軍の大将妖怪は、実在した武将だった!?古典妖怪「大ガマ」と細川勝元の伝説
2016年8月14日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 … 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】Aランク ゴーケツ族「ヒライ神」は「古事記」と「ギリシャ神話」から着想を得た?
2016年8月13日 ATLASEDITOR ATLAS
※本コラムはゲーム作品「妖怪ウォッチ1~3」をアカデミックに解析し元ネタの特定ほか妖怪伝承について解説していくコーナーです。 …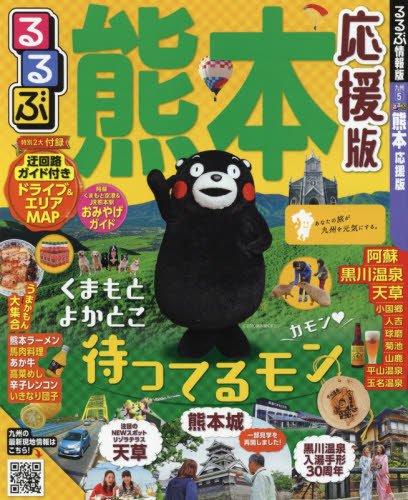 妖怪
妖怪【妖怪ウォッチ研究序説】妖怪はゆるキャラだった!?本家が認めた奇跡の妖怪「ケマモン」とは?
2016年8月13日 ATLASEDITOR ATLAS
「妖怪ウォッチ2」から登場した新しい妖怪にプリチー族の「ケマモン」がいる。ケマモンは主人公の祖母が住む「ケマモト村」の「ご当地妖怪」としてケ … 妖怪
妖怪全国で「ピカチュウ」大量発生中!ダンス中に縮むピカチュウも!?
2016年8月13日 ATLASEDITOR ATLAS
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「ポケモンGO」 … 妖怪
妖怪海水浴は妖怪に注意!?これが海に現れる妖怪たち
2016年8月11日 ATLASEDITOR ATLAS
夏休みになり、日本全国で暑い日々が続いている。全国の海水浴場などで海のレジャーを楽しむ人は多い。 さて、広い海には昔から様々な妖怪が住 … 妖怪
妖怪【実話 怖い話】赤子淵
2016年8月11日 ATLASEDITOR ATLAS
これはかつてRくんという私の友人から聞いた、彼の体験談の独白である。 うちの叔母の家の近くには、川の流れが大きく歪み地面が削れたところがある。昼でも暗く、流れのない澱んだ淵に … 妖怪
妖怪【怪談実話】姑獲鳥(うぶめ)が訪問する家 奇妙な足音(その1)
2016年8月9日 ATLASEDITOR ATLAS
「山口さん、鳥の妖怪っていますか?」 突然、彼女から電話がかかってきたのは、数年前の秋の初めであったと記憶している。 「どういう … 妖怪
妖怪【怪談】薮の中
2016年8月3日 ATLASEDITOR ATLAS
ある夏の事です。私は、白い蛇がじーっと私を睨んでいるのに気付きました。見ることが出来れば幸運が訪れるという白蛇がいるだけでもビックリなのに、まさしくその物とにらめっこしているのです …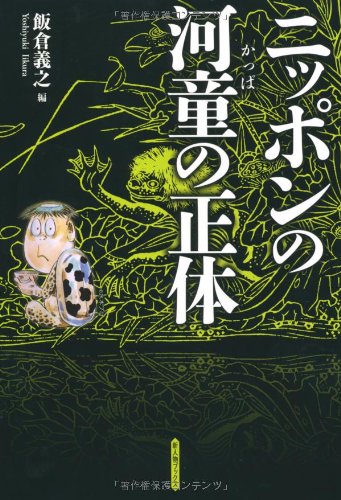 妖怪
妖怪「ポケモンGOで河童と対戦?」
2016年8月3日 ATLASEDITOR ATLAS
巷ではポケモンGOが大流行しているが、残念ながらポケモンGOに熱中するあまり、恐ろしい事件が起きてしまっているのも事実だ。 その1つが、北海道でポケモンを探していた大学生が野 … 妖怪
妖怪【怪談実話】百物語
2016年8月2日 ATLASEDITOR ATLAS
Sさんがまだ学生だった頃、大学の運動部で多摩の某お寺に合宿に行きました。その時の話です。 日中はハードなトレーニングを行い、夜は毎晩宴会でした。そして合宿1週間目に入った頃、 … 妖怪
妖怪【妖怪】隠し婆
2016年8月1日 ATLASEDITOR ATLAS
皆さんは隠し婆という妖怪を知っていますか。 地方によっては隠し神、子とり婆とも呼ばれ親の言った事を聞かず、夜遅くまで遊んでいる子供達を魔界にさらってしまうという恐ろしい妖怪で … 妖怪
妖怪【怪談実話】這う老婆
2016年8月1日 ATLASEDITOR ATLAS
Fさんは某商社に勤めるエリート社員でした。当然残業も多く、常に帰宅も深夜でした。それでもFさんは愛する妻の為、日々懸命に頑張り続けていました。 妻とは恋愛結婚でした。スキー場 … 妖怪
妖怪【怪談実話】死を呼ぶ子供
2016年8月1日 ATLASEDITOR ATLAS
埼玉のある病院に入院していた人から聞いた体験談です。 その女性Vさんは内臓を煩い、1ケ月近く入院していました。同室の方とも仲良くなり気心もしれてきたある夜の事です。 夜 …