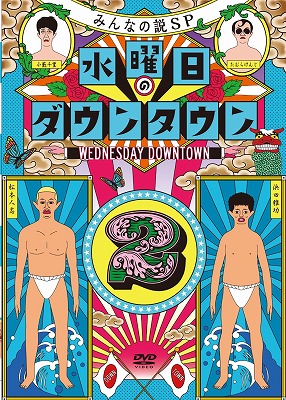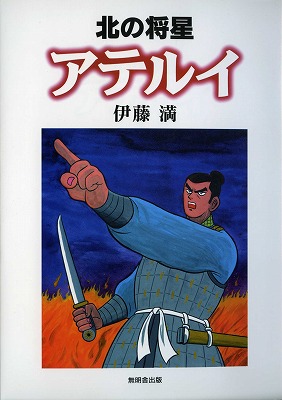日本武尊(やまとたけるのみこと)は、大和朝廷の日本統一に貢献した古代の英雄であると同時に、最期は悪神によって殺されてしまう”悲劇の王子”として日本人から愛されてきた。義経しかり、坂本龍馬しかり、我々日本人は志半ばで死んでしまう気の毒な英雄に心惹かれるみたいだ。
無論、実在の人物ではないと推測されており、大和朝廷の日本統一事業において貢献した複数の人物をモデルして創作された架空の人物である。特に素盞嗚尊(スサノオノミコト)との共通点も多く、そのキャラクター育成においてスサノオの属性をモデルにした可能性はありうる。
例えば、スサノオが姉であるアマテラスとトラブルを起こし、高天原から下界に追放されるエピソードは、兄を殺してしまい父親に疎まれ熊襲討伐に向かわされたヤマトタケルと似ている。さらにスサノオは妻であるクシナダヒメを櫛に変えて自らの髪に差し、ヤマタノオロチと戦って勝利しているが、ヤマトタケルは海に身投げした妻であるオトタチバナの櫛を見つけ悲しみに暮れている。
また、ヤマトタケルが使った草薙剣は元々スサノオがヤマタノオロチの胎内から取り出したものである。以上の類似点を考えると、やはりヤマトタケルはスサノオの再生神ではないかと解釈するのが妥当である。
古事記をもとにヤマトタケルの人生を振り返ってみよう。第十二代景行天皇の第二子として生まれ、幼名は小碓と言った。小碓は武勇に秀でていたが気性が激しく、兄・大碓を些細な喧嘩から殺害してしまう。このあたりまさに人格が破たんしている。父である景行天皇はこの暴挙を聞くに及び、小碓を遠ざける為に九州の熊襲(クマソ)の平定に行かせた。
小碓ことヤマトタケルは、叔母のヤマトヒメから女性の衣装をもらい、女装して熊襲建(タケル)兄弟に接近、見事暗殺に成功する。この時に熊襲建から「倭建命(ヤマトタケルノミコト)」の名をもらうのだが、女装してターゲットを殺害する行為にも何やら暗殺行為を楽しんでいるような様子が伺える。だまし討ちはヤマトタケルの得意技だったようで、出雲国でイズモタケルを暗殺した際も、剣を木製の剣にすり替え暗殺に成功している。
無事に帰京したヤマトタケルであったが、今度は東国の征討を言い渡されてしまう。
ヤマトタケルは叔母のヤマトヒメに「父は自分が死ねばいいと思っているようだ」と話して嘆き悲しんだ。このあたりから分析すると叔母に母親に近い母性を感じていることが伺え、父親に認めてもらいたくて凄惨な暗殺劇を繰り返してきたようにも思えてくる。
東国へ向かう旅路の途中、相模国造に騙され火攻めに遭うのだが、持っていた天叢雲の剣で周囲の草を刈りとり、叔母から貰った火打石で迎え火を焚いて難から逃れる。この時より天叢雲の剣は草薙剣(くさなぎのつるぎ)と呼ばれるようになった。
ヤマトタケルは三浦半島から房総半島に渡る際に大きな過ちを犯してしまう。この海を見ながら「このような小さな海は一跨ぎだ」と海を小馬鹿にする発言をしてしまったのだ。この発言に激怒した海神は、海を渡っているヤマトタケルの船を嵐で苦しめた。今にも沈没せんといった状態になった際、同行していたヤマトタケルの妻・弟橘比売(オトタチバナヒメ)が海神の怒りを鎮めるために身投げをしてしまうのだ。
やがて嵐が静まり、ヤマトタケルたちは無事上総(千葉県)に渡る事ができた。そこでヤマトタケルは海岸に落ちていたオトタチバナの櫛を見つけ、悲しみに暮れるのであった。
因みに千葉県の地名には、この伝説に由来するとされているものが幾つかある。「木更津」は妻を想い、なかなかヤマトタケルが立ち去らない様子を現した「君去らずや」という言葉から生まれたとされており、「袖ケ浦」は身投げした妻の袖が流れ着いた事から名付けられたとも言われている。また「蘇我」はイオトタチバナが漂着し蘇生したため、その地名が生まれたとされている。それにしても、この悲劇は全てヤマトタケルの軽口から生まれたものである。
東北を平定したヤマトタケルは尾張に立ち寄り、婚約を交わしていたミヤズヒメと結婚する。オトタチバナヒメが亡くなった後の、この変わり身はヤマトタケルの性格をよく表している。その後、ミヤズヒメに草薙剣を預けたまま、素手で伊吹山(岐阜・滋賀県境)の神を退治しに出かけるが、神に打ち負かされ、失神してしまう。
このあたり散々だまし討ちで敵を倒してきたヤマトタケルとは思えない油断である。前後不覚のまま山を降り、ふもとの泉の水を飲んで回復をするが、とうとう命を落としてしまった。ヤマトタケルの死を知った妻や子は駆けつけ陵を造り、その周りで歌を詠った。するとヤマトタケルは大きな白鳥となり空高く飛び去ってしまう。
まさに悲劇の英雄の名にふさわしいヤマトタケルの物語だが、実際には大和朝廷の日本統一事業で活躍した性格破綻者の皇子や豪族など数名がモデルになっているのではないだろうか。
(山口敏太郎 ミステリニュースステーションアトラス編集部)