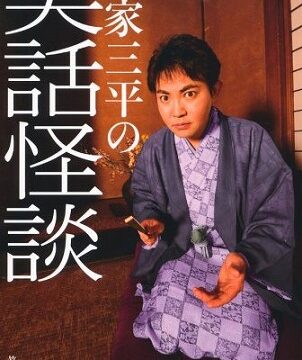Rさんは、首都圏の平凡な大学をごく普通の成績で卒業し、地方の小さな会社に勤めた。
「しようがないじゃん。この不況の影響でさ、女一人じゃ、関東では生きていけないんだから・・・。涙の都落ちみたいなものよ」
彼女は時々そうつぶやいては、自嘲気味に笑う。だが、目元は笑っていなかった。一度は首都圏で就職する事を望んだが、この不況では職もなく、実家の母親の友人が経営する会社にコネで入社したのである。
「一度は故郷を捨てて関東に逃げたあんたがどの面さげて帰ってきてんの!って感じで幼なじみに嫌みを言われましたしね」
Uターン組の彼女は地元では少々肩身が狭いらしい。しかし、母親の紹介してくれたこの会社には満足していた。この会社の業務は、地元の出版物や町内会の名簿、運動会のパンフなど地域密着の印刷物を取り扱うものであった。
「Rちゃんがうちの娘だったらな~」
人の良い社長はいつもお茶を飲みながら豪快に笑った。この社長を入れても、10人に満たない少人数のその会社は、家庭的でアットホームな雰囲気であり、都会で心が傷付いた彼女にもやさしく対応してくれた。
(この会社なら、ずっと働きたいな~)いつしか、彼女は徐々にそう思うようになっていた。
それから、一年が経った。大夫仕事に慣れて来た彼女は、事務所に出入りしていたある業者の営業マンと仲良くなった。十代のころに少し不良だったと称するその男は、同性や異性にかかわらずいろいろと配慮のできる性格で、そのきめ細かい気配りや、まめなフォローにいつしかRさんは惹かれていった。
「俺なんか、ずっと地元でしょ、なんかRさんみたいな都会の香りのする人って憧れるんだよね」
緊張しながらしゃべる朴訥(ぼくとつ)な男は、大層魅力的に見えたのだ。当然、二人が交際するまで時間はかからなかった。勿論、デートをかさね、肉体的な関係も結んだ。首都圏にいたときにはRさんも大学時代のボーイフレンドと経験済みであったし、男は商売女で随分と遊んでいたために、将来結婚するとかもわからない二人であったが、性に対する考えはそんなに保守的ではなかった。
交際してから半年ぐらいたったある日のことだった。彼女は、自分が妊娠していることに気が付いた。(あの男の子供だわ)Rさんは酷く落胆した、この頃になると、男との関係も冷め切っていて、お互いに顔を見るのもイヤになっていたのだ。
(どうしょう、あいつに言ったところで、堕胎しろって言うだけだろうし…)彼女は悶々と悩み、社長に相談した。親身になって聞いてくれた社長は、男の会社の役員とも協議し、二人に話し合いをさせた。だが、男は最後まで抵抗した。
「俺はまだ父親になりたくない、責任を持てない」
こう繰り返すばかり、いっこうに拉致があかない状態であった。
「もういいです、自分で生んで育てます。あなたには何も求めません」
彼女は、男にそう言うと、絶縁した。
(都会に見放され、田舎では男に騙された)Rさんは泣きながら、車を運転しながら自宅まで帰路を急いだ。(ああ、見栄は切ったけど、どうしよう。自分一人で育てることなんかできない、生んだって母さんに迷惑かけるだけ、どうしょう。やっぱり、おろすべきなんだわ)彼女は泣きながらハンドルを回し続けた。
すると、道ばたで手をあげている子供がいる。どうやら、小学生ぐらいの男の子のようだ。
「どうしたの?こんな夜遅く、家まで送ってあげようか」
車を止めた彼女がそう声をかけると、男の子は黙って頷いた。ドアをあけると男の子は、助手席にのってきた。
「おうちの番地はどこ?」「○○2丁目○○」
その番地は、彼女の実家のそばであった。(おかしいわ、近所にこんな子供いたかしら?)Rさんは、不審に思いながら、車を進進ませた。
途中、男の子は黙っていた。初めて見る子供であったが、何故か懐かしい気がした。また、その横顔は何故か実家の母親に似ていた。(不思議ね。この子といると妙に落ち着くわ)そう思いながら、車を自宅の前に止めると男の子に声をかけた。
「貴方の家もこのあたりね。早く帰りなさい」
大きく頷くと男の子は車を降り、車外に飛び出した。そして2、3歩、走り出すと、振り向くとこう言った。
「お腹の赤ちゃん、生まれたがってる。だから、生んであげて…」
そういうと男の子は闇の中に走っていった。
驚いた彼女は後を追ったが、既に男の子の姿は闇に溶けて見えなくなっている。(どういうこと?あの子はなぜ、私の妊娠がわかったの?)言いしれぬ不安感を感じた彼女はそそくさと自宅に入った。
翌日、町内会の役員に問い合わせたが、該当する男の子の消息は不明であった。
それから、一年後、働きながら子供を育てるRさんの姿があった。彼女は笑ってこう言った。
「あの時の男の子の一言で、私は産みたいと決心したんです。ほら、観てくださいよ。この子の横顔、あの時の男の子そのまんま…。私はね、この子があの時の男の子に変わって姿を現したんだと思ってるんです」
(山口敏太郎 ミステリーニュースステーション・アトラス編集部)
※画像 ©PIXABAY