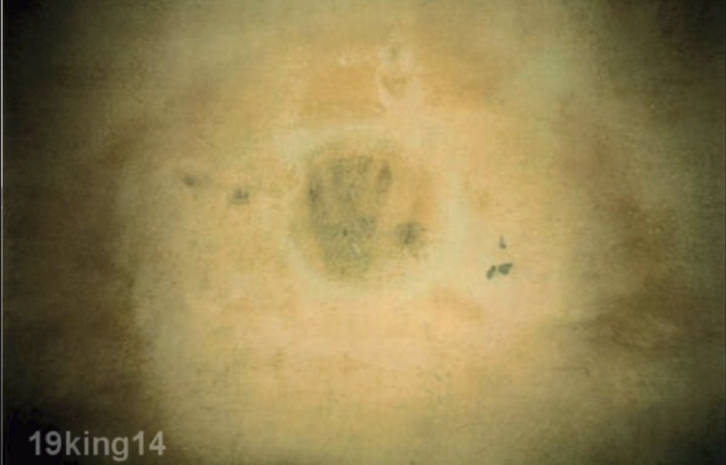Oさんは、千葉県八千代市にある某企業の営業所に勤務している。彼の職場は、誰でも知っている大企業だ。
「エリートは東京にいる人でしょうよ。僕は全然ですよ。今は目の前の仕事をやるだけですから…」
彼は謙虚に語る。だが、同時にその目には仕事に対する自信が伺える。
この会社は、バリバリ働くイメージがあるのだが、地方の職場はのんびりとしているそうだ。営業所の周辺には、森や川も周辺にあり、自然に囲まれたこの職場を、彼は心より愛していた。
「だって、朝なんか小鳥の声がうるさいぐらいでね、夏場は昼にセミの大合唱ですよ。これがまた賑やかななんです。それに、会社の近くは夜になると本当の真っ暗ですよ。あれこそ、闇夜っていうんですかね」
笑顔をたたえながら、満足気に語るOさん。
フラボノたっぷりの空気は、仕事の疲れを癒してくれるのだという。因みに彼は、この夏で、会社に入って十五年目になる中堅社員だ。上司からもそこそこ難しい仕事をまかされている。だから、バブルの忙しい時期も、景気崩壊直後の不況シーズンも経験済なのだ。
彼が新人時代、この営業所に勤務した初日、“いやな話”を聞いた。
…先輩社員の 自・殺・話 であった。
「あなた、新人だから知らないのね、この営業所のニ階でね…」
先輩社員が教えてくれた話によると、この営業所のニ階にある更衣室で、先輩社員が自殺したのだという。
「みなさん、宜しくお願いします」
この先輩社員は、本社に勤務する役員のご子息で、幹部候補生として入社した。だが、その血統の良さが災いした。逆に周りの同僚から妬まれ、嫌がらせをされ、精神的に追い込まれていった。
「あのお坊ちゃんに、仕事やらせろよ」
「エリートさま、やってもらえば…」
その苛めは陰湿なものであった。ひとりだけ、大量の残業を押しつけられたある日の真夜中。そして、彼は更衣室で首を括った。
翌日、遺体は発見され、社内がパニックになった。
「うおおおお」
慟哭する本社の父親。だが、虐めた同僚たちの処分は曖昧であった。勿論、いたたまれなくなってやめたものもいるが、中には今も居座っている厚顔無恥な同僚もいるらしい。
「俺は関係ないね」
そう言ってとぼける同僚。
こんな話を聞いたOさんは、なんとも言えない気持ちになった。(酷い話だ、それにしても、なんて連中だ。僕はそんな社員にはならない…)
こんな気持ちを胸に秘めながらOさんは、仕事に取り組んできた。
こうして入社から、五.六年がたち、Oさんも役職をもらった。月末の〆の作業にも携わるようになった。毎月の売り上げの計上作業なのだが、どうしても深夜までかかってしまう。
「やっても、やっても終わらないんですよ」
彼はそう言って笑う。
そんな時は真っ暗闇の中、営業所だけが煌々と電気がつき、山野を照らずのだという。
「まさに峠の一軒家って、感じですよ。日本昔話みたいだね」
このような作業が毎月続くうちに、Oさんは妙な出来事に気が付いた。毎月、電話がかかってくるのである。
「誰だ、こんな時間に」
その電話をとってみると…。
「あれっ、発信は社内だな」
そのコールは、…内線である。だが、電話に出ても相手は何も言わない。
――無言なのだ。(なんだ、この電話は、こんな夜中に内線だって、誰がこんな夜中に…)考えて見ると、内線は営業所内部しか使えない。深夜は役職者のみ、この部屋で〆作業をやっている。
(おかしい、誰か残っていたずらしているのか、そんなことはないはずだが)誰もいない構内のどこかから、内線電話がかかってくるのだ。
「ちくしょう、気味が悪いな」
無論、電話の故障の可能性もあるので、電話業者に調査をさせたが異常はなかった。その後も、この月末の怪電話は続いた。
ある月の〆の夜、また電話が鳴った。
「よし、犯人を捕まえてやる」
仕事そっちのけでOさんは、必死に社内を探した。―――だが、誰もいない、のである。
(どういうことなんだ、霊なのか? 人間じゃないのか)捜索が終わった後、Oさんは気味が悪いので自分の受話器をはずしていた。
「もう邪魔するなよ」
Oさんは見えない相手につぶやいた。つまり、通話中なら内線もならないのであろうと思ったのだ。だが、また電話は鳴った。
「……!!?」
恐怖におののくOさん。彼はある決心をしてニ階にあがった。
「おまえは、ここにいるんだろう!」
更衣室のドアを開けた。するとテーブルの上におかれていた電話が内線通話状態になっていた。
(やっぱり、ここだったのか)彼は黙って受話器を戻した。なんともいえない気分になった。
「先輩、まだ迷ってるんですね」
Oさんは、ひとり更衣室でつぶやいた。
それからも月末の無言の内線電話は続いた。やはり、志半ばで亡くなった先輩社員の霊が、後輩を心配しているようだ。
「あまり、無理をしないように」
首を括った先輩は、今も電話をしてくれているのであろうか。霊は孤独で真っ暗な更衣室から、今も内線電話を廻し続ける。
(山口敏太郎 ミステリーニュースステーション・アトラス編集)