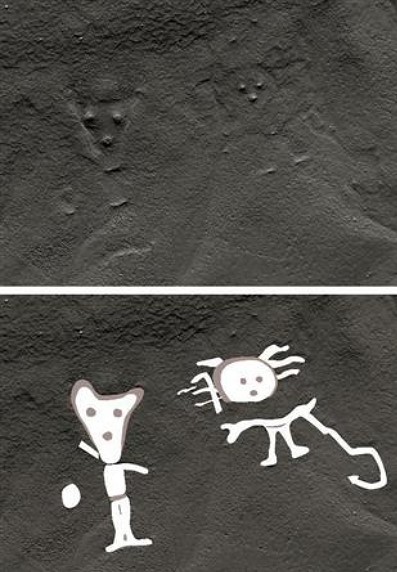2回目の投稿となります。ゆかりんです。さて、今回は私自身の不思議体験を2つ送らせていただきます。
私は20代半ばから趣味でフィギュアスケートを習っていたのですが、20代後半からは職場の先輩と一緒にピアノも習っていました。看護師という激務に加え、だからこそ精神的な安定のために趣味を楽しんでいました。やるからには趣味であっても成長し続けたいという思いが強くなり、スケートとピアノの二足の草鞋ではなく、どちらかにひとつにしぼってより集中して取り組みたいと考えるようになりました。
そんな折、夜勤を終えた後のことです。術後の患者さんの転入や他の患者さんの不穏などがあり、非常に忙しかったことを覚えています。
私も頑張ったけど、同僚も頑張ってくれた。激務を終えた達成感と疲労に襲われていました。心身ともに疲弊していたにも関わらず、私はその後高速道路を飛ばして40~50分ほどかかるスケート場に向かっていました。
高速を降り、一般道の大きな交差点で信号待ちをしていた時の事です。
直進レーンで時々意識が飛びそうになるのをこらえながら「スケートとピアノ、そろそろどちらかに決めなくちゃ。」とぼんやり考えていました。
すると突然、大きな耳鳴りに襲われました。言葉や映像ではなく、頭に瞬間的に響く嫌な予感。
私はとっさにバックミラーを見ました。すると信号待ちしている私の後ろから、何十トンあろうかという大きなトラックが猛スピードで迫っているではありませんか。
私は驚きながらも「どうか間に合って!」と思い、確認もせず右折レーンに車を滑り込ませました。
運よく右折レーンは空いており、後続車も来ていません。接触する?ギリギリよけれた?と思うと同時に、信号無視をしたまま大きなトラックは猛スピードで私のすぐ左横を通り抜けて行きました。
もしあの大きなトラックを避けられなければ、私の運転していたプジョー206は小柄なためペシャンコになり、私は即死していたと思います。
交差点ではしばらく時が止まったかのように、どの車もしばらくの間、全く動きませんでした。青信号のはずの交差する車道の車も、トラックの迫力に押されたのでしょうか、全く動く気配がありません。
右折レーンでとまっていた商用車のおじさんは、驚いたような表情でこちらを見ていました。
視線が突き刺さり恥ずかしさと怖さと安心とで泣けてきました。
今度はこちらが青信号になったところで直進レーンに戻り、追いかけてトラックを確認しよう、トラックを管理する運送会社に文句を言ってやろうと思いましたが、そのトラックはすでに走り去っており、近くで大きな事故も起きていないようでした。
人に言うと驚かれるのですが、私はそれまで教習所以外でバックミラーを見たことがありませんでした。バックする時もドアを開けて直接目視していました。サイドミラーも同様で確認のために見たことはなく、スーパーの狭い駐車場に駐車する際、サイドミラーをたたみ、開くことを忘れて自宅に帰ることがよくありました。
ミラーを見ないため、たたまれていることにもそもそも気付かないのです。しかしこの経験を通して、きちんとミラーでも確認するようになりました。
「スケートは大怪我するリスクも高く、仕事を抱えながら、遊びじゃできない。高速道路で居眠りしたら死んじゃうし。」
そう再確認し、ピアノに専念することに決めました。
考えてみれば直前にいろいろなサインが出ていたように思います。当時いたスケート仲間のうち、一番真面目に練習していた方が練習中に足を骨折するという大怪我に見舞われました。私が「今日は滑りたくないな…調子が悪いかも。」と思う時は、決まって私ではなく、同行していた主人がスケート場で肩の脱臼や大きな転倒をしていました。
信号待ちで感じたあの強い嫌な予感は何だったのか、普段見ないバックミラーをなぜ見たのか、そう考えると今でも不思議です。そしてこの時から強く感じるのです。「ああ、私は生かされているんだ。何か役目を背負って生きているんだ。」と。
あともう一つ。
まだ弟たちが近くにいなかったため、私が幼稚園に上がった頃、40年近く前の出来事かと思います。
私は母に連れられて、地元ではおしゃれな婦人服専門店にいました。店主のおじさまと母は立ち話をしています。私は母と手をつないで「大人の話は長いなー。」と思って聞いていました。
店主のおじさまはスタイルはすらっとされていて、髪は薄めですがロマンスグレー、品よく整えられています。そして眼鏡をかけた知的な感じのする紳士でした。
いつしか年齢の話になり「私はこの髪のせいで年上に見られるんですよ。」「いくつに見えますか?」と母に質問されていました。
母がまごまごしていると、私の頭の中に突然「58」という数字が浮かんだのです。
それはまるで、当時のテレビのブラウン管に真っ黒い画像が映し出され、白抜きで数字が浮かんだようでした。
私は当時からおしゃべりな子供でしたが『多分58歳なんだけどな。手をつないでるから手から気持ちを送るんだけど、お母さんじゃ伝わらないだろうな。』『でも私からは言っちゃいけない気がする。』と思い、黙っていました。
するとおじさまが急にこちらを向き「お嬢ちゃん、おじさんいくつに見える?」と質問してきました。
『聞かれたならば答えてよい。』となぜか感じたため、即「58!」と答えました。
おじさまはそれを聞くや否や非常に驚かれ「えー!すごい!お嬢ちゃん何でわかったの?」「ほおー。これはすごいわ。」としきりにおっしゃっていました。
しかし、もともと天然の母はあまり驚いた様子もなく、ぼーっとそれを聞いているだけだったように記憶しています。ひょっとしたらこの出来事自体、母の記憶からは消えているかもしれません。
(アトラスラジオ・リスナー投稿 ゆかりん ミステリーニュースステーションATLAS編集部)
Photo credit: FotoSleuth on Visualhunt.com