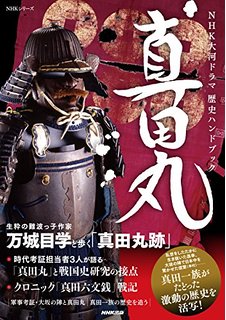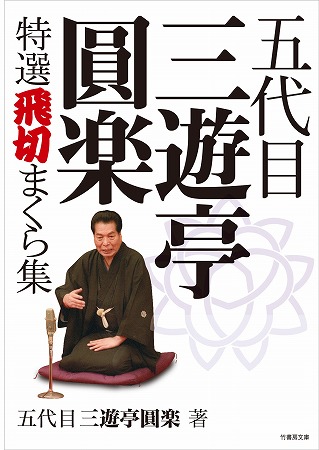Wさんはもう何十年の警備員をやっている。
若い頃に流行った警備員を扱ったテレビドラマに憧れ、この世界に入った。だが、ドラマのように劇的な活躍はないのだが、実直な人生を確実に生きてきた。
そう、唯一の奇妙な体験を除いては・・・。
「あのビルには、もう絶対に行きたくありません」
彼はそう述懐する。
あれ今から十年近く昔の事だ。Wさんは都内のビルの夜間警備に配属された。
「ぜひ、やらしてください」
そのビルは産業スパイ事件に巻き込まれており、警備が厳重になされていた。彼ぐらいベテランになると夜間警備などで現場に出ることはないのだが、敢えて最前線の現場に身をおいていたのだ。
「じゃあ、行ってきます」
「はい、何かあればこちらに連絡ください」
モニターを監視する仲間を警備室に残し、Wさんは夜間の巡回に出かけた。昼間の喧騒が嘘のように、静まり返っている。そのギャップが恐怖と違和感を生み出すのであろうか。また夜間のビル巡回ほど、怖いものはない。
「特に問題はないようだな」
彼は自分に言い聞かせるように言った。
夜間警備の場合、侵入者に複数の警備員がいるように見せかける為、一人で対話しているかのようにしゃべることもある。
―――もっとも、この夜は怖さを紛らわすためでもあった。
ビルの最上階まで行った時、まだ残業しているOLがいた。薄明かりの中で机を整理している。
「遅くまで、ご苦労さまです」
Wさんは嬉しげに声をかけた。人がいるのは、やはり安心する。すると、女は振り返りこう言った。
「去年のデータがないんですよ」
人形のように無表情な女。
彼はこの女に得たいのしれない恐怖を感じた。
「大変ですね、手伝いましょうか」
そう言って女の横にいくと、彼は異常な臭気を感じた。
―――焦げ臭い
肉をこげるまで焼いた匂いである。
(なんで、肉がこげる匂いがするんだ)彼がそう思った時、女が書類を床にばら撒いた。
「わあああ、こんなもの、こんなもの」
「落ち着きなさい」
必死にとめるWさん。だが、女の狂気は暴走する。髪の毛を逆立てて、書類を投げ捨て、足で踏みにじっている。終いには、書類に火をつけ、紅蓮の炎を見て笑い始めた。
「ふははははっ、いい気味だわ、燃えてしまえばいいのよ」
女はそう言って笑いながら、己の衣服にも火をつけ始める。
「あああ、そんなことしちゃ 駄目だよ」
おろおろするWさんを余所目に、女の全身が火に包まれた。女の顔に忽ち皺が入り、老婆のような顔になる。
「ひゃあああああああああ」
女の髪の毛が火に包まれ‥。女の絶叫が響き渡る‥。
「なんてこった・・・」
その地獄絵図を見て、へたり込むWさん。そこに、監視カメラを観ていたはずの同僚が駆けつけた。
「大丈夫ですか Wさん!」
その声にふと我に返るWさん。
「おお!いいところに来てくれましたね、女の人が自分に火をつけて‥」
そう言って指差す方向には何もいない。静まり返ったオフィスがあるのみである。
「ええっ、さっきまで女性がいたはずだが‥」
驚くWさんに同僚はこう言った。
「あれが千年OLです。元々あの女の幽霊は、このビルで自殺したOLだったんですよ。何年も、何十年も同じシーンを繰り返してるんですよ」
Wさんは、愕然とした顔で言った。
「じゃあ、彼女は‥」
「そうですね、百年でも千年でも同じ事をやってるんでしょうね」
Wさんは、そのビルの担当を一日で辞めた。
(山口敏太郎 ミステリーニュースステーション・アトラス編集部)
画像 ©PIXABAY