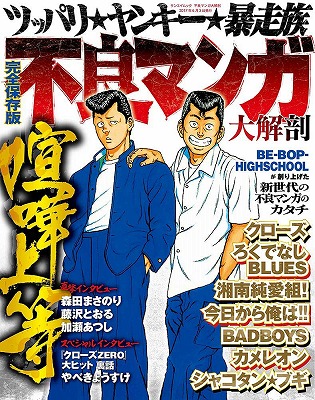第4の事件が発生する直前、1888年9月25日、切り裂きジャックと名乗る人物から犯行声明文が新聞社のセントラル・ニューズ・エイジェンシーに届いた。その内容によると、切り裂きジャックは女の体を商売に使う売春婦を毛嫌いしている事、警察には絶対に捕まらない事、犯行はまだまだ続くという内容であった。
しかし、この手紙の事が新聞で報道されると、1日あたり平均20通近くの犯行声明が届き、その後の犯人の犯行声明文がどれなのかわからなくなった。
また1888年9月30日、エリザベス・ギュスターフスドッターとキャサリン・エドウッズの2人が殺害されているが、この犯行現場には異様な落書き文があった。
近くの壁にチョークで書かれた乱雑な文書の内容は、あまりにも政治色の強いものであった。「ユダヤ人は正統な理由もなく責められるべき人間ではない」という文章で、ユダヤ人に対する不当な差別を引き起こす可能性があった。
この不気味な一文を見たトーマス・アーノルド警視は、夜が明けてロンドンの市民がこの落書きを目にしたら、一般大衆の反ユダヤ的な感情を煽り、暴動のようなものが起きるのではないかと感じた。
結局、警視はこの落書きを消させたが、現場写真ぐらいは残すべきであったという意見も噴出し、捜査の混迷の一因となっている。無論、切り裂きジャックとユダヤ人の関係は不明であり、大部分のユダヤ人が善良な市民であった事は明白である。
果たして、切り裂きジャックの正体は誰であったのか。
一時はヴィクトリア女王の孫であるクラレンス公爵も容疑者にリストアップされるなど捜査は大混乱に陥り、人々やマスコミの憶測をよそに事件は迷宮入りしてしまう。ジャックは闇に消えたのだ。
切り裂きジャックの正体が歴史の闇に消えた後も犯人探しは続いた。当時、捜査に加わっていたドナルド・スワンソン警部の手書きメモが発見され、子孫の手によってスコットランド・ヤードの犯罪博物館に寄贈された。
このメモは、事件当時にスコットランド・ヤードの警視監であったロバート・アンダーソンの本の裏ページに記入されたもので、切り裂きジャックの重要容疑者について記載されていた。そこには、ポーランド系ユダヤ人アーロン・コズミンスキーが重要容疑者として記載されている。
日頃から重度の精神障害を煩っていたコズミンスキーは、実妹をナイフで脅すなど数々の奇行で捜査線上にのぼっており、証拠があがれば身柄を確保する予定であったが、唯一の目撃者であったユダヤ人が、同じユダヤ人を告発できないと証言を拒否し、逮捕まで及ばなかった。
結局、コズミンスキーは1919年、北ロンドンのコルニー・ハッチにある難民施設で天寿をまっとうする。
最近では米国の推理作家パトリシア・コーンウェル女史が、切り裂きジャックが投函したとされる切手に付着したDNAから、犯人のDNAを割り出し、そのDNAと一致する当時の人物を特定したのである。
著名な画家であるウォルター・シッカートのDNAと、犯行声明文のDNAが一致したと公表したのだ。
だが、既述の通り、切り裂きジャックの手紙とされるものは多数残されており、果たしてその手紙を書いたものが本当の犯人なのか、或いは事件に便乗した悪戯犯なのかは判らない。つまり、犯行声明を書いた人物=真犯人と確定されない以上、DNAの判定の意味はないのである。
この冷ややかな世間の反応に対しパトリシア・コーンウェル女史は新たな証拠を盛り込んだ本を発表するというが、果たして万人を納得できる内容になるかどうか、注目したいところだ。
近年になり、イギリスで再び惨劇が繰り返される。
イギリス南東部のサフォーク州イプスウィッチ近郊で、切り裂きジャックを彷彿させる陰惨な事件が発生したのだ。
売春婦5人が切り刻まれ、殺害されるという連続殺人事件に「21世紀の切り裂きジャック」と世界中で大騒ぎになった。犯行現場と思われるイプスウィッチ近郊において、2007年12月に入り女性の遺体が次々と発見された。身元を調査してみると、最近行方不明になっていた19歳から29歳の売春婦5人と判明した。
捜査が困難な状況にも関わらず、警察は町の各所に配置されたカメラに被害者たちが写っている時間から殺害時間を割り出した。
また、サフォーク署のスチュワート・ガル警視正は、被害者全員と面識があり、事件当時のアリバイのない大手スーパーマーケットの従業員(異説には運転手という記事もある)トム・スティーブンスを容疑者として逮捕したと公表した。
だが、この男は逮捕前にもマスコミのインタビューに対して無実を訴えており、後日新たな容疑者であるスティーブンライトが逮捕され、釈放された。
果たしてこれで事件は本当に解決したのであろうか。今後新たな猟奇殺人は、起きないのであろうか。
精神科の医師は、患者の狂気に触発されてしまうというが、ジャックの持つ狂気が他人に影響を及ぼすとしたら、ジャックの亡霊は数十年後に三度復活するのだろうか。
(ミステリーニュースステーション・アトラス編集部)