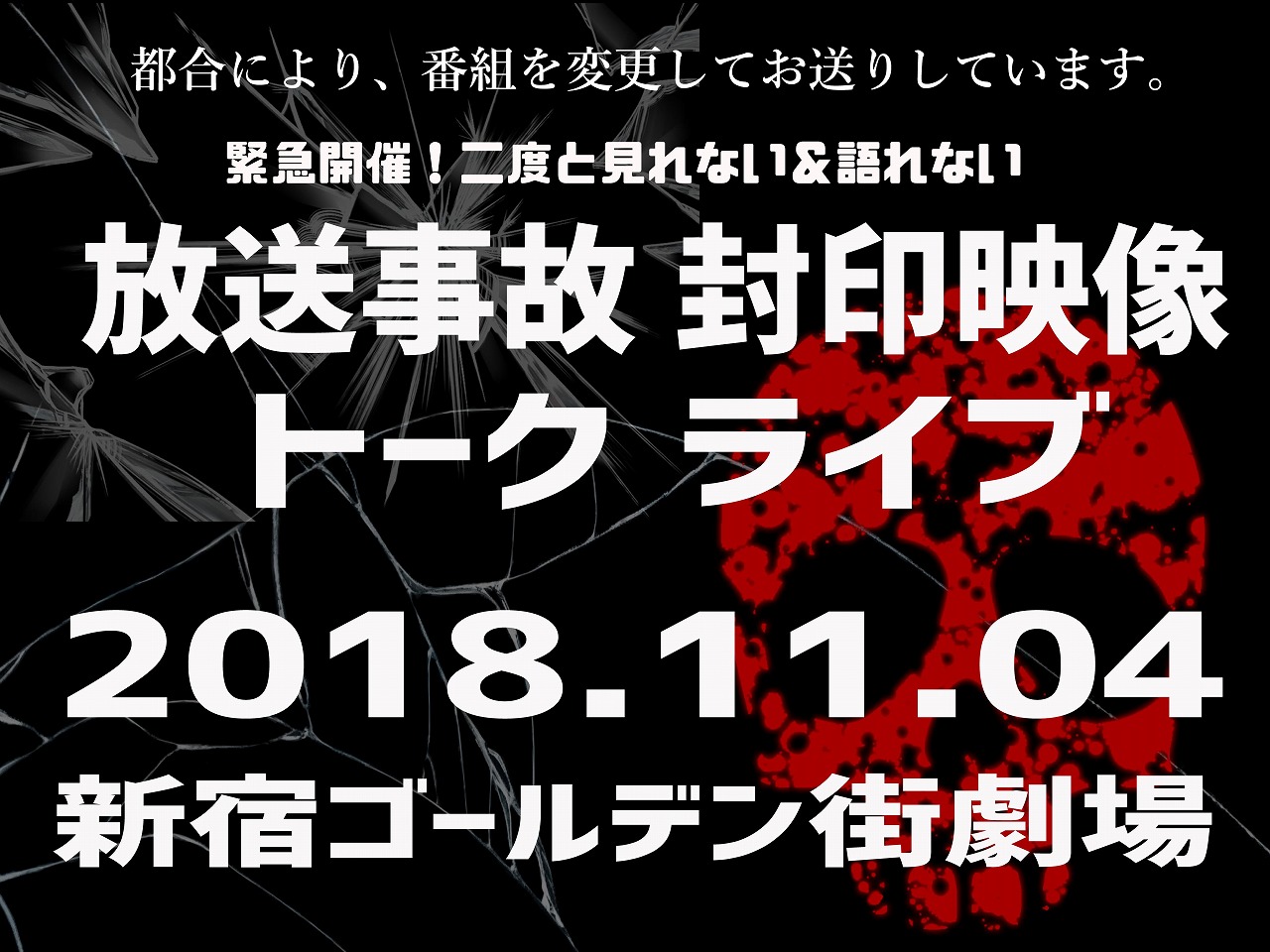度々世間を騒がせる偽札事件。近年は安価で成功な印刷が可能になったため、ニュースになることも多い。だが透かしや記号等の様々な偽造防止策までは真似することができず、偽造の犯人は逮捕されることになる。
だが、中には全く偽造が解らなかった事件も発生していた。
1961年12月7日に発見された「チ-37号事件」である。
この日、日本銀行秋田支店にて廃棄予定の千円札の中に、奇妙な紙幣が発見された。他の札に比べてやや薄く、手触りが微妙に違っており、通し番号の数字が不揃いだった。
警察はこれを受けて紙幣偽造事件として捜査を開始。多くの県で流通していた偽札が発見されたが、後に不揃いだった通し番号の数字を直したものが発見された。

犯人が偽札の報道を受けて、より真券に近くなるように修正したのである。
この「バージョンアップされる偽札」はその後も改良を重ねながら発行されつづけ、最終的には22都道府県から343枚が発見されるに至った。
最後に発見されたのは1963年11月、紙幣の図案が切り替わる直後であった。
偽札を作り続けていた犯人には様々な説が流れていたが、結局判明しないまま事件は1973年11月4日に公訴時効が成立し、未解決となっている。
(勝木孝之 ミステリーニュースステーションATLAS編集部)