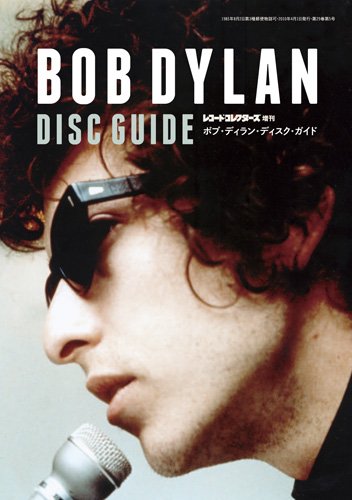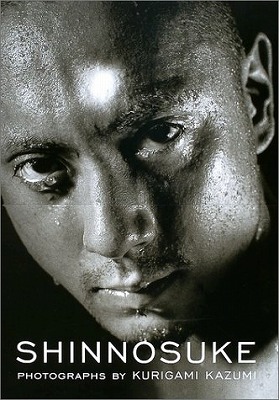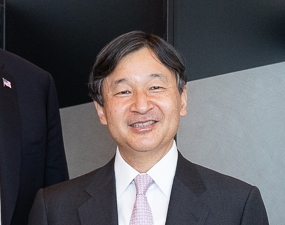市川市役所の向かい側に「藪知らず」という史跡がある。
この森に入るものは二度とでれないとか、呪いを受けるとか様々な噂が江戸期から言われている。
伝統的な魔所であるが、国道14号線に接し、頻繁な車の往来にさらされており、往時の恐怖は微塵もない。いささか興ざめだが、こんもり茂った森の入口には、小さな鳥居が鎮座している。
筆者の友人が以前、この森の伝説に反発し、この鳥居をまたぎ、森の内部に侵入したことがある。筆者の眼前での蛮行であったため、口あんぐりの状態でみていたが、
「科学が全てに優先し、伝説・伝承などはなんの価値もない」
という概念の友人(後に幽霊に遭遇し、考えを改めるが…)であったため、祟りとか呪いとかはまったく気にしない。その後、数ヶ月して彼の祖父が死亡した。
「ほら、やっぱり祟りがあったんだ、噂どおりだろう」
という筆者の言葉にも
「いや、祖父の死は、単なる偶然だと思う…」
と主張して一歩も引かなかった。偶然と言えども、私はそういう行為の因縁を感じた。
この「藪知らず」はいったい何故、入らずの森になったのであろうか。伝説では、水戸黄門がこの森に入り込み沢山の妖怪に襲われたと伝えられている。そして、黄門の前に白髪の老人が出現し、
「この場所は人間の来る場所ではない」
と諭され、以後水戸黄門の指導により、長く同所は禁足地となり、今に至るとされてきた。だが、実際は水戸黄門と言えども、自国の水戸藩領内ならともかく、他人の土地でそんなお節介をやくだろうか。
調べていくと、江戸期は水戸黄門ではなく、ヤマトタケルがこの藪知らずに入ったという伝説にされており、水戸黄門伝説ができたのは、黄門漫遊記が庶民に浸透した明治以降のようである。つまり、時代時代の人気ヒーローが藪知らずに入った事になっているのだ。
なぜこのような不思議な伝説が広まったのであろうか。その謎解きについて多くの研究家・好事家が仮説を披露している。
他にも伝説以外に呪術的解釈も広く喧伝されている。元々将門軍の本陣の死門(かつて同所にあった立看板によると、仙道で言う鬼門という意味らしい)があった場所であり、将門敗北以降、不吉とされたとも、将門配下の七騎武者が同地にとどまり息絶えたとも言われている。呪術的には、なんと禍々しい場所であろうか。
また現実的な解釈としては、他領の飛地であったため、近隣の住民の侵入が禁止されたという説や、将門を討ち取った朝廷側の陣地であったため、将門びいきの地元住民が避けたという説もある。これらの説は現実的でさもありなんと言ったところであろうか。
なおこれは筆者のオリジナルの解釈だが、藪知らずの藪は鬼門の護り(あるいは裏鬼門)ではないだろうか。神社の鬼門に藪を設置する考えは、新編武蔵風土記にその伝説は報告されている。鳩ヶ谷中居村(現鳩ヶ谷市八幡木)の八幡宮の鬼門に竹藪があり、その中の木に触れると祟りがあるという記述である。
特に八幡は武芸・戦争の神として源氏系の武士の信仰を集めたが、鬼門封じとしても珍重された。頼朝が幕府を開いた時、鎌倉幕府の鬼門を守るために「鶴岡八幡宮」を創建したことはあまりにも有名である。
つまり、八幡は都市や組織の鬼門を護る霊的システムであり、同時に八幡自身の鬼門・裏鬼門は「藪」に護らせたのではないだろうか。言い換えれば鬼門封じの二重らせん構造である。
となると、「八幡の藪知らず」とは、何かの鬼門封じの残骸かもしれない。ちなみに「藪知らず」から北東(鬼門)の位置には、「葛飾八幡宮」が存在する。つまり、「藪知らず」は「葛飾八幡宮」の裏鬼門(南西)を守護している事になる。当然「葛飾八幡宮」の鬼門にはもうひとつ別の神社が存在している。
このことから推理すると、「葛飾八幡宮」を霊的に守護する為、鬼門、裏鬼門に「鳥居を伴った藪」が配置され、いつしか千葉街道に面した裏鬼門の「藪知らず」のみ有名になってしまったのではないだろうか。
同時に謎めいた史跡であるため、明治以降も多くの怪異談も派生している。幾つか列挙してみよう。
藪の中に機織りをする女性がいるという。どうにも怪しい女らしいのだが、その女性が機織りの器具を借りに来た事がある。
「貸してくださいませんか」
随分と物腰が柔らかい。道具を貸してやると、翌日返しにきたのだが、返却時に血がついていたという。いったい何を織ったのであろうか。このあたりは、中国から伝来した七夕信仰の影響がある。
ちなみに、藪の中に女がいるというのは千葉県北部に伝承される「藪っこの天女」と、関連あるいは、混同があるのかもしれない。ちなみに「藪っこの天女」とは、藪の中に住む美女であり、若い男を藪に招き入れてしまう妖怪のような存在である。
つまり、伝説が場所を生み、場所が新しい伝説を生むのであろう。伝説と史跡は互いに影響しあいながらエピソードを創り上げるのかもしれない。
(山口敏太郎 ミステリーニュースステーション・アトラス編集部)