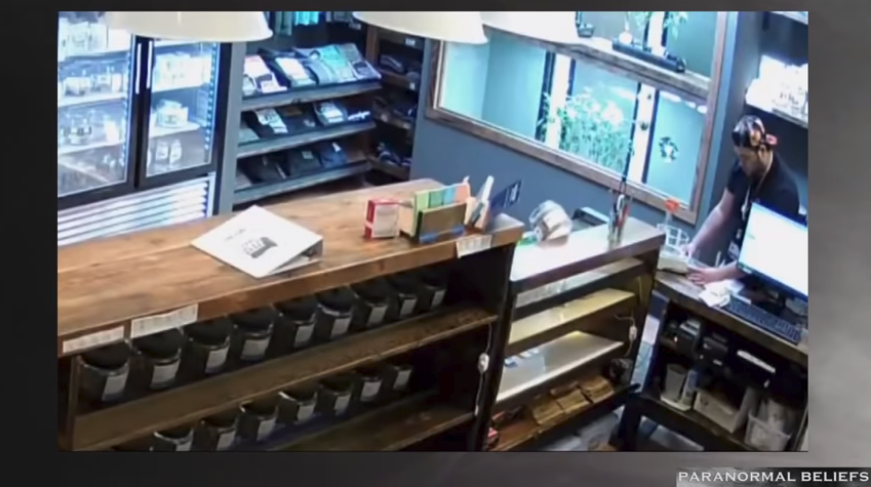或る年の事、某寺にて百物語が開かれた事があった。この寺の小僧が大層物好きで、若い仲間を集めて百物語をやろうと提案したのだ。
「せっかくの夏じゃないか、怪談でもやろうじゃないか」
「そうだ!どうせやるなら、江戸の作法で本格的にやらないか」
小僧と仲間たちは喜々として準備に勤しんだ。薄暗い本道には、無骨な蝋燭が百本据え付けられた。淡い焔が本堂の壁に揺らいでいる。
今回の趣向は、別室で怪談を一話語り、終わった話り手は、そのまま本堂へ行って一本の蝋燭を吹消し、帰路に着くというものである。
「この趣向だと、後になる程、怖いじゃないか」
「そうよ、最後に残る程、豪の者ということになる」
人々は不安げに囁いた。つまり、最後はまったくの一人になってしまうのだ。
「ひいい、俺からやらせてくれぃ」
大勢集まったのだが、臆病者から先にやり、段々と夜が更けていった。最後に小僧と刀屋の息子、莊屋の息子の3人が残った。
「この三人しか残らなかったか」
小僧がぽつりとつぶやいた。
灯は二本となっている。
「じゃあ、私がひとつ」
刀屋の息子が怪談を語り、一本の蝋燭が消え、最後の灯りのみ残った。
「では、最後は私が語ろう」
莊屋の息子が言った。
主催者の寺の小僧が見守る中、莊屋の息子が語り終わり、本堂で最後の蝋燭が消された。
「…」
莊屋の息子は、しばし、その場所に留まった。だが、特に変わった事は起こらない。
(終わった、だが怪異など起きないじゃないか)莊屋の息子は、鼻で笑った。
莊屋の息子が語り部屋に帰ってくると、寺の小僧と、刀屋の息子が待っていた。
「どうでした? 何かありましたか」
小僧が聞いた。
刀屋の息子も、百話目に何か起こるか気になったらしく、自分の話を語り終えた後も、自宅には帰らずそのまま待っていたのだ。
「何もおきやしないよ」
莊屋の息子は、無愛想に言った。
「そうか」
刀屋の息子は、少々がっかりしたようだ。
「それより、お二人、夜も更けた事ですし、今宵は寺にお泊まりください」
小僧の薦めで、二人は寺に泊まることになった。一緒の部屋に三人で川の字になって寝始めたが、百物語の興奮がおさまらない。
特に莊屋の息子は、いつまでたっても寝つかれなかった。
(いかん、まったく寝れない)耳には二人の寝息が響いてくる。こうなると余計に寝られない。
ふと、隣に寝ている小僧の夜着を見た。何者かが、馬乗りになっている。莊屋の息子は恐怖で全身が硬直した。
(あれは、いったい、なんだ) 酷く痩せ、頬のこけた女の幽霊が、小僧の横に立っている。
無論、小僧は熟睡している。
(なんだ、あの女は…)恐怖のあまり、莊屋の息子は夜着の下でぶるぶると震えた。間違いなく生きている人間
ではない。
女の幽霊は、小僧の夜着を持上げると、「ふう~」と息を吹いた。
(なにをしたんだ、あれは)上下の歯ががくがくと揺れ、どうにも噛み合わない。小僧の精気を吸い取ったのであろうか。
女の幽霊は、音もなく移動した。今度は、刀屋の息子の上に馬乗りになった。暫く、すると、女の幽霊は、刀屋の息子の夜着を持ち上げると「ふう~」と吹いた。
またしても、精気を吸われたのであろうか。
「おい、大丈夫か、おい目を覚ませ」
莊屋の息子は、恐怖に震えながらも二人の名を呼んだ。…だが、返事がない。
(もう死んでいる。今度は自分の番なのか)と思うと恐ろしくて、頭の中が真っ白になった。
女の幽霊は、青白い顔をこちらに向けた。
(来るな、こっちに来るな)莊屋の息子は、心の中で叫んだ。
すると一番鶏が鳴いた。
「朝か、朝が来たのか」
女は霧のように消えていった。
後には、二人の死骸が残されている。命拾いした莊屋の息子は、以来信心深い男に変わった。
(助かった、もうあんな恐ろしい目には逢いたくない)莊屋の息子は、その足で氏神様に祈りに行った。
「こうして、祈ることで魔物を遠ざけたいのだ」
莊屋の息子は必死だった。
こうして、毎日のように氏神様参りを続けた。すると、どういうわけだが、帰り道いつも同じ女に会う。
「こっ、こんちわ」
「いつも、熱心ですね」
最初は挨拶程度だったが、満願の日にはすっかり心やすくなり、いつしか二人は深く愛し合うようになった。そして、二人は夫婦になった。そして、それはそれは幸せな暮らしを送っていた。
夫婦となり、しばらく経った或晩。妻が台所へ行ったものの、なかなか帰ってこない。
「どうした、なにかあったのか」
莊屋の息子が覗くと…。
妻が火を吹いていた。
「ふっ~」
「あああっ、あの横顔は…」
その顔は先年、寺で見たあの女の幽靈であった。
(そう言えば、百物語は去年の今夜であったな)莊屋の息子は、ぞっとしながら部屋に引き下がった。
―――妻は死者だったのか
今、妻が背後に立っている。
(山口敏太郎 ミステリーニュースステーション・アトラス編集部)
画像 ©写真素材足成