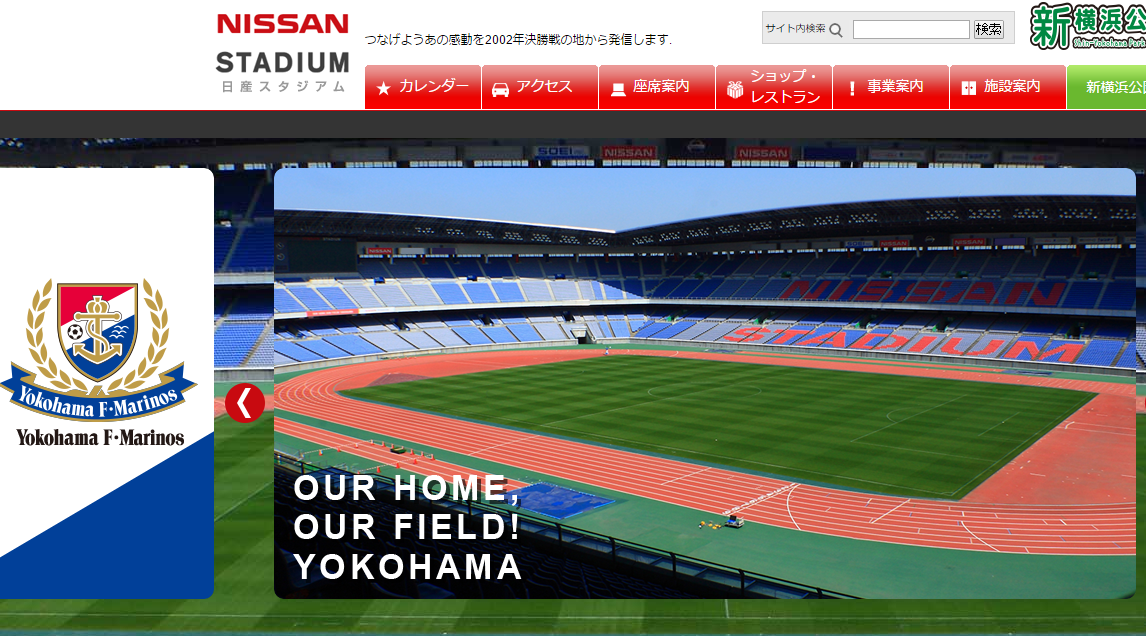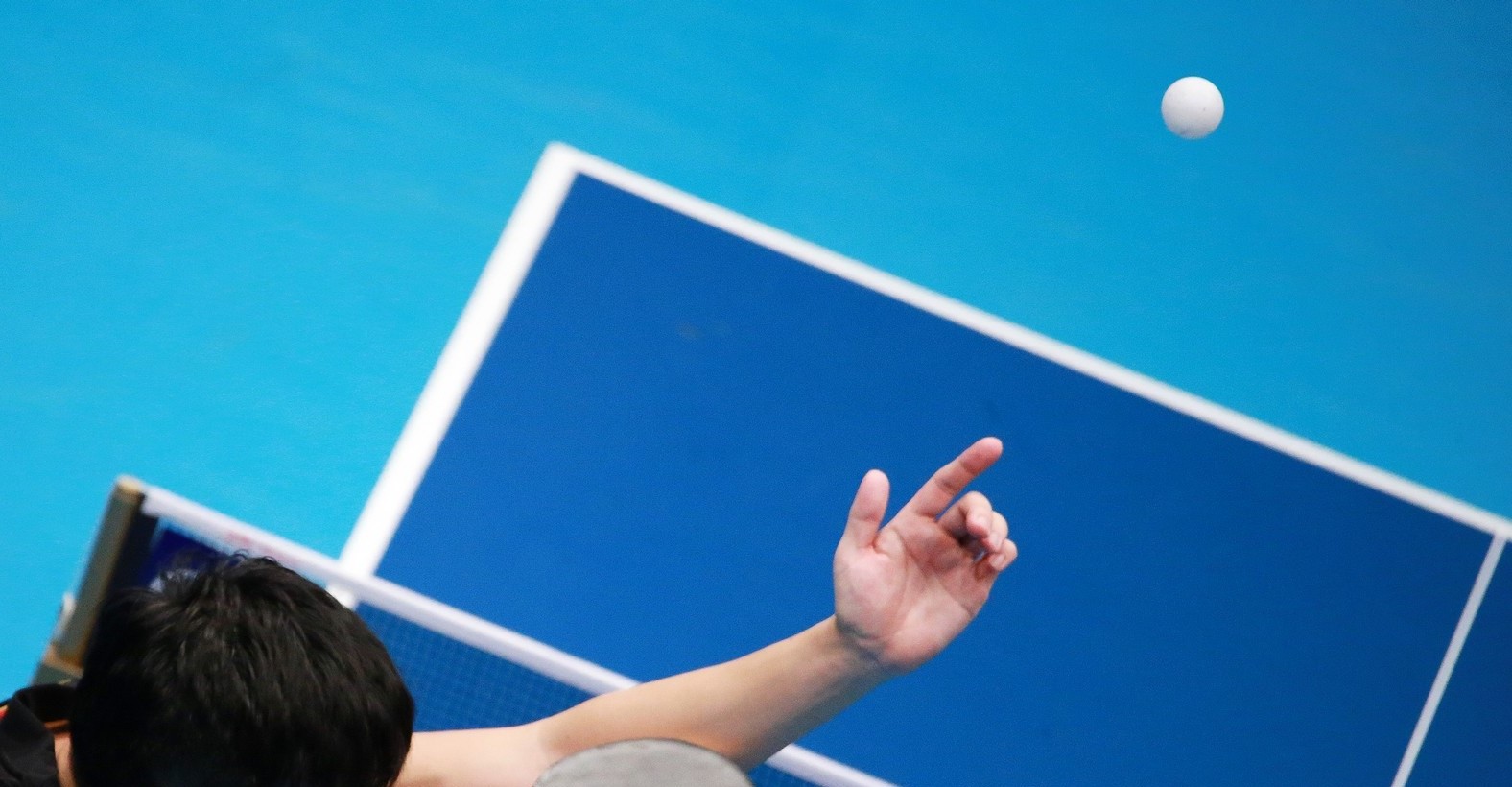Tさんは宅配便のドライバーであった。元々は金属メーカーで製造に従事していたが、大の運転好きが高じてドライバーの道に転向してしまった。
宅配便の仕事は、朝6時に会社の仕分け場で荷物を積み込み、朝8時には既に配達を始めてなければならない。そのくせ夜間の配達希望も多く、夜の21時近くまで走り回る毎日であった。それ故、帰宅してもそのまま眠るようなハードな生活が続いた。
だがTさんは満足であった。大好きな運転が仕事に出来たのである。こんな嬉しい事はない。毎日が充実していたのだ。そんな生活が一年ぐらい続いた時であろうか。Tさんは担当エリアの変更を現場の所長から命令された。
「Tくん、せっかく慣れたところなのに悪いね。エリアを変わってもらえないかな」
「まじですか!今のエリアには思い入れがあるんですが…」
Tさんは、ややふてくれたようにつぶやいた。そんなTさんの表情を見ているのか見ていないのか、所長は構わず話し続けた。
「頼むよ。Tくんの気持ちはわかるが、ほら、君も御世話になったYさんが老い先短いんだよ。例の病気、いよいよヤバいらしいんだ」
「ええっ!!Yさんって、そんなに悪いんですか」
Yさんとは、Tさんの先輩ドライバーで、この道30年以上のベテランであった。50代半ばのYさんは先月から入院しており、いよいよ危ないらしいのだ。その為、Yさんの配達担当エリアをTさんに担当してもらいたいというわけだ。
迷ったTさんであったが、新人時代、親切に指導してくれたYさんが大切にしていたエリアを守ることが、自分の使命だと思えてきた。
「T君よ、僕ら宅配ドライバーは近所の皆さんに顔を覚えられてなんぼだよ。僕は自分のエリアのお客さんから荷物を受け取る時、荷物を届ける時、何とも言えない喜びを感じるんだ」
Tさんの脳裏には元気だったYさんの言葉が甦ってきた。
翌月、Yさんのエリアを配達するTさんの姿があった。1週間ぐらい配達していると、集荷先の常連さんやいつも届けるお得意先とも馴染み、段々とやりがいを感じるようになった。
ある時、Tさんは事務所から集荷指示の電話を受けた。
「あっ、Tさん、○○番地○の▲▲さんが集荷をお願いしたいそうです」
「個人宅の集荷ね。了解」
Tさんは快く答えたが、事務所の受付係の女性は一言付け加えた。
「あの~この▲▲さんって、Yさんも警戒していた怖い人なんで…気をつけてください」
(…怖い人だって)Tさんは一瞬考えこんだ。とんでもない頑固親父がいる家庭なのか、神経質な方なのか。
そして、Tさんは恐る恐るその家の前に車を停めた。
「ごめんください」
Tさんの呼びかけに誰も答えない。家はシーンと静まりかえっている。
「ごめんください」
呼び鈴を押しながらもう一度呼んでみる.すると、か細い声で応答があった。
「裏に回ってください」
Tさんは裏口に回ってみた。すると梱包された荷物と運賃がちょうど置いてあった。
「ありがとうございます。確かに受け取りました」
Tさんは受領書を置くと、その家をそそくさと立ち去った。
(何となく、やな感じの家だったな)
Tさんはその家の不気味さにうんざりしていた。何とも言えない恐怖を感じてたのだ。
その後も、時々荷物が届いたり、荷物が出されたりしていた。集荷の時は荷物と現金が裏口に置かれており、配達の時は裏口の窓にかかった薄暗いカーテンの向こうから声が聞こえ、荷物を受け取る白い手が見えるだけであった。
(おかしいぞ、絶対、あの家は変だ)
それから半年ぐらい経った時の事。その家に配達に行った帰り、近所のおばさんが顔色を変えて呼んでいるのに気が付いた。
「どうしたんですか?」
「あんた、あの家に配達に行ったのかい」
「ええ、そうですが」
「だったらやめなさい。あの家は一家惨殺事件があった家で、今は誰も住んでいないんだよ」
「そんな馬鹿な・・・」
Tさんは焦った。あの白い手は幻だったというのだろうか。そんなワケない。確かにこの眼で見たんだ。
Tさんは焦ってその家にもう一度戻ると・・・、家は廃墟の如く朽ちており、人の住んでいる形跡は無かった。
(今までのは何だったんだ。俺は一体どこに配達していたんだ。あの手の主は誰なんだ)
そう思いながらTさんは立ちつくした。
Tさんは今も思っている。多分、あの白い手は黄泉の国から来た死者の手だったのだろう。また、Yさんが病気になったのは死者の荷物に関わりすぎた為だろう。そして、宅配便を使っているのは必ずしも生きている人間だけに限らないという事を。
(山口敏太郎 ミステリーニュースステーション・アトラス編集部)