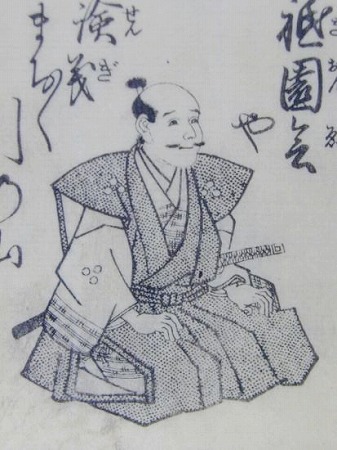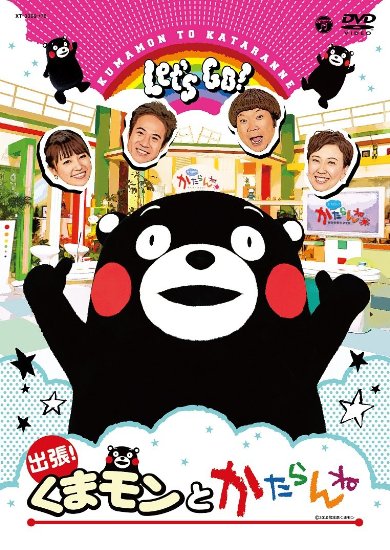安土・桃山時代、豊臣秀吉の御伽衆(側近)として仕えていた人物であると言われている曽呂利新左衛門は、落語家の始祖とも言われており、その頓智の利いたユーモア溢れる数々の逸話で知られている人物である。落語家としての名跡は二代目の死後は空きとなっているが、特に初代については伝説的な逸話が数多く語られている。
彼は元々、刀を収める鞘を作る職人であったという。職人としての腕がよく、彼の作る鞘は刀が「そろり」と抜き差ししやすかったということから、曽呂利と名乗るようになったと言われている。
秀吉に使えるようになったきっかけは、朝鮮出兵にて遠征軍が堺から出立しようとしていた頃のこと、出立の日は町をあげて大がかりなお見送りをすることになっていたのだが、何度も延期になっており町の皆が迷惑していた。すると、その出立の延期を繰り返すことを揶揄した歌が出回り、怒った秀吉によって犯人を捜すよう命じられた結果、その歌は曽呂利が詠んだものであった。
ところが、曽呂利を直接尋問したところ、秀吉は彼のユーモアある物言いをすっかり気に入ってしまい、仕えさせることを決めたという。
曽呂利の機転は、一休に劣らぬものであったようである。
ある時、秀吉のお気に入りであった松が枯れてしまい、管理役を咎めようとしていたところに曽呂利が「誠におめでとうございます」と秀吉に言った。「何がめでたいのか」と秀吉が聞くと、彼は紙と硯を用意し「御秘蔵の常世の松は枯れにけり己が齢を君に譲りて」と詠み、秀吉は「なるほど松の木は自分の身代わりになってくれたのか」と喜び、誰も咎められずに済んだという。
こうした秀吉を持ち上げる頓智は多く、秀吉が猿に顔が似ていることを嘆いていると「猿の方が殿下に似せたのです」と言って笑わせたこともあったという。
その彼の逸話で最も有名なものの中に次のようなものがある。
ある日、曽呂利に褒美を与えようとした秀吉が彼に何が欲しいかを尋ねると、「初日は米1粒、2日目は2粒、3日目は4粒と一ヶ月間、前の日の倍の米粒を下さい」と申し出た。「そんなことでよいのか」と聞き入れた秀吉であったが、この計算でいくと一ヶ月後にはおよそ200俵という尋常ではない量になってしまうことに途中で気づき、慌てて別の褒美に変えるようお願いしたという。
権力者を頓智でやり込めるという話は江戸・明治ごろに多く誕生しており、先に触れた一休を含め多くの頓智めいた逸話が創作されたと言われている。曽呂利の逸話も、このような経緯によって数多く生み出されたとする説が強いようであり、そもそも初代の彼自身が架空ではないかという説まであるほどだ。
その一方で、毒舌で知られた立川談志も、一休以上の洒落た人物として蜀山人(太田南畝)と共に好んだ人物として名前があがったのも曽呂利であった。一説には、戦国から江戸前期ごろの浄土宗僧侶で、笑い話を集めた『醒睡笑』を著したと言われる安楽庵策伝と同一人物ではないかとの説もある。
【参考記事・文献】
曽呂利新左衛門と豊臣秀吉~世相を表す頓智の逸話
https://nihonsizatugaku.net/sorori/#toc3
曽呂利新左衛門【御伽衆】秀吉の暇つぶし、頓智で笑わす…
https://sengoku-history.com/2017/09/02/sorori/
秀吉をあわてさせた「ヤバい計算」
https://diamond.jp/articles/-/240078
【アトラスラジオ関連動画】
【文 ナオキ・コムロ】
画像 ウィキペディアより引用