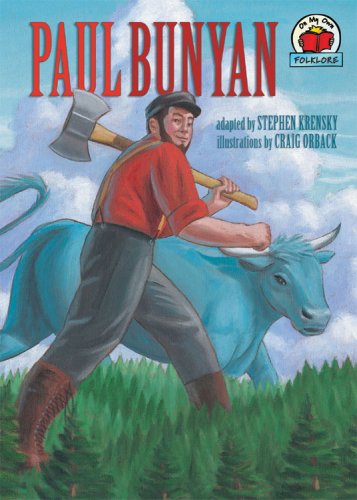十数年ほど前の話。
夏に、学校で合宿(厳密には合宿とも違うが)があった。
夏場だったので、肝試しとして百物語を教室でやる事になった。
人数は20人ほど。机を教室の後ろに片付け、椅子を円形にぐるりと並べ、灯りを落として一人ずつ怖い話を順繰りに出し合っていった。
だが、そのうちの一人が、1周目から
「俺、怖い話知らないから」
と言って、話そうとしない。その為、皆も2週目以降は一応確認するものの、さして詮索する事もなく、百物語は彼をとばして進んでいった。
しかし、もともと参加人数が少なかったので、ひとりあたま4話も5話も話さなくてはならない。
そのうち怪談のネタも尽きはじめ、ネタが切れた者から例えば『悪の十字架(=この店、開くの十時か?)』系のギャグでオチを付けるタイプの怪談を話すようになっていった。
本当に怖い話も、ただのギャグ話も混じっての百物語は、初めから「怖い話知らない」と言っていた彼で、ちょうど百話目を迎える事になった。
「これが最後なんだし、何でもいいからお前も話せって」
「いや、俺本当に知らないから」
「別に怖くなくてもいいし。あの、お笑い系でもいいからさ。」
「いや、本当に知らないんだって」
皆で口々に言って聞かせるが、なかなか彼は話そうとしない。
「だって、俺のめっちゃ怖いから! いやマジで半端ないから!」
「怖いならちょうど良いじゃん。言えばいいのに」
「いや、マジ洒落にならんよ?」
「いいじゃん、シメに良いよ」
すると彼は、少し迷って、こう言った。
「・・・・・・じゃあ、言うけど・・・・・・絶対に逃げんとってな? 置いてくなや?」
「別に逃げんよ。言ってみ」
確認するように言った彼は、周りの反応を見て、やがて意を決したように口を開いた。
「最初からこうなんやけど・・・・・・俺の足下、見て」
床から白い手が出て、彼の足首をぎゅっと掴んでいた。
途端、教室は蜂の巣をつついたような騒ぎになり、みんな蜘蛛の子を散らすように教室を出ていった。
落ち着いたところで、廊下で人数を確認してみたが、やはり1人足りない。彼が居ないのだ。
まだ教室の中にいるのだろうか。
そう思って覗いた友人達の目の前には、すっかり正気を無くし、虚空に向かってへらへら笑っている彼の姿があった。
彼はそのまま合宿を切り上げて帰る事になった。そして、夏休みが開けても彼は学校に出てこなかった。
先生や家族に聞くと、あれから心神喪失状態で病院に入院したままだという。無期限の長期休学扱いになっていた。
彼の様子が気になるし、逃げんとってな、と言ったにもかかわらず逃げ出した事に対する罪悪感もあるしで、仲の良かった友人数人が見舞いに行く事になった。
病院に行くと、彼の母親が出迎えてくれた。
「会っても良いけれど、話ができるか分からんよ・・・・・・。話す事が出来ても、全く意味の分からない事ばかり言っているし・・・・・・」
やつれたように見える彼の母親は、見舞いに来た友人達を気遣うように言って、部屋に通してくれた。
病院の天井を、焦点の合わない目でぼーっと見ている彼に、友人達は一人一人声をかけていった。「大丈夫か」、「気分はどうや」、「また学校来てな」・・・・・・
だが、彼らの声を聞いた途端、彼が急にベッドから跳ね起きた。
そして、友人達の顔を見据えて、こう叫んだ。
「なんで逃げたあぁ!!」
今までは明らかに、所謂『病気の人』の様子だった。
なのに、叫んだその一瞬だけは、明らかに正気の人間のものに戻っていたと言う。
彼は今も、自宅で病気療養中だという。
彼が正気を取り戻したのは、後にも先にも、あの一瞬しかない。
(ミステリーニュースステーション・アトラス編集部)