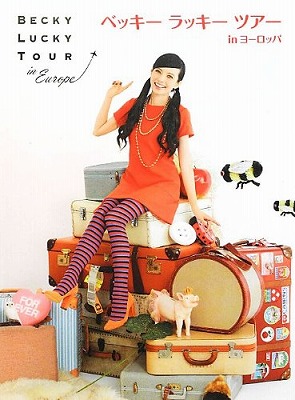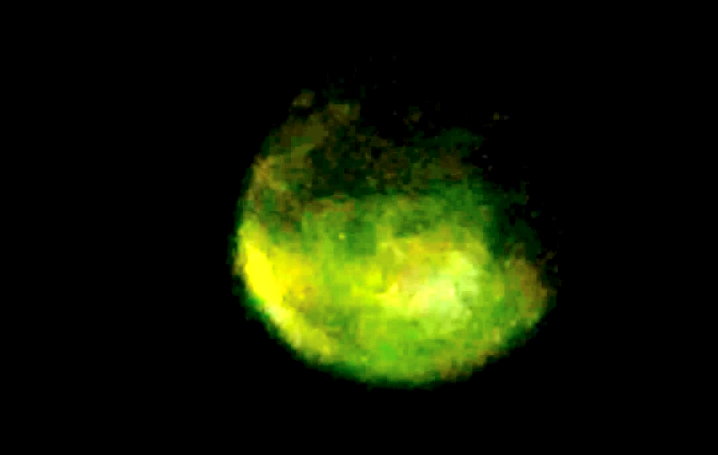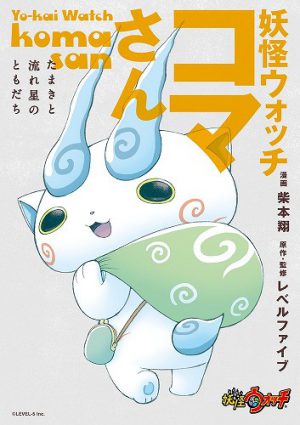日本映画界の都市伝説に以下のような話が残っている。
昭和20~30代頃、とある映画会社ではこの頃徐々に頭角を現してきた中堅の監督による時代劇の製作がはじまっていた。
この監督はチャンバラシーンでの血の流し方には人一倍強いこだわりをもっており、この日も遅くまで血のシーンを撮影していた。
ただし監督が特に頭を悩ませられたのは、川の流れにそって流れていく血のシーンであった。
当時、撮影用の血のりは質が非常に悪く、川に流れる前に溶けてしまうか、重すぎて水に沈んでしまうものがほとんどであった。そんななか、助監督のひとりが茶碗一杯分の血のりを持ってきて「監督!これを使ってください!」と差し出した。
さっそく助監督が差し出した血のりを使ってみたところ綺麗に血が流れだした。
しかし、そのシーンは人がひとり死ぬ場面なのでどう考えても茶碗一杯分では量が足りない。
そこで監督はバケツ一杯分の血のりを要求し助監督を走らせ、ようやく血のシーンは完成した。
しかし、助監督は完成を見ることなくまもなく死亡してしまったという。もうお分かりだろう。助監督の用意した血は自分自身に流れていた血だったのである。それならリアルなシーンが撮影できるわけである。
この事件の後、血の出るシーンを撮影する際は必ず、ニワトリや豚といった血のり用の動物を同行させるようになったというが、あまりに出来すぎている話だけに真実かどうかは不明である。
(ミッチェル横山 ミステリーニュースステーション・ATLAS編集部)
※画像 ©PIXABAY