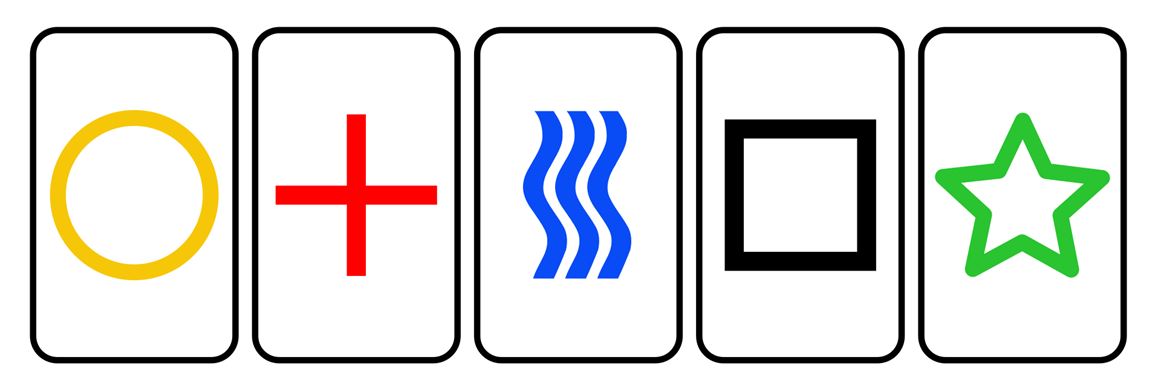人間は誰しも幸運になりたいものである。特に成功している立志伝中の人物などにその傾向が強い。
人はいくら金持ちになっても、いくら成功しても、その上をめざす。欲望に上限はないのだ。
ある企業の創業者T氏もそうであった。彼は東京の下町に生まれ、父親から受け継いだ個人商店レベルの会社を、大企業に育て上げた凄腕の経営者なのだ。
今は、隠居の身だが、高度経済成長期、彼は働きざかりであった。
「うちの会社を日本一、いや世界一にしてみせる」
それが彼の口癖であったのだ。
当時、日本は好景気に沸いていたのだが、先見の明があった彼は不況時に耐えうる企業づくりを目指していた。
「不安だ、なんだかよくわからないが不安だ」
常に彼の心中は漠然とした不安に覆われ、その恐怖から追われるような圧迫感を感じていた。
ある年の夏、彼は長野の某飲食店で奇妙な人物と出会った。白い髭をたっぷりと生やし、ボサボサの白髪は不潔な印象を与えた。この店のオーナーとは古い顔なじみらしく、何も注文しないのに、悠然とお茶だけを飲んでいる。
「ほほほほっ おまえはまだ何か足らぬものがあるな」
(なんだ、この老人は、俺の心をみすかしている)警戒しながらもT氏は、老人の横に座り直した。
「ご老人、私の心が見えておいでのようで…」
「わしぐらいの年になるとな、人の心の声が聞こえるんじゃ」
(なんだ、このじいさん、いい加減なことを言って何者だ)
訝しげに睨んだ彼に、老人はこう言ってのけた。
「おまえ、わしの事を いい加減なことを言って何者だと思ったであろう」
あまりの衝撃に全身を硬直させるT氏。老人はにやにやと笑いながらお茶をすすっている。
(どういう事だ、やっぱり人の心が読めるのか)恐怖のあまり、額に脂汗をかきながらT氏は老人を見つめた。
「そうじゃよ、おまえさんの思うとおり、やっぱり人の心が読めるのじゃ」
こんな事があるのか、T氏は老人に自分の心が全て見透かされているという得体の知れない恐怖感で耐えきれなくなった。
すると、老人はその漠然として恐怖をなだめるようにこう続けた。
「いいかな、若いの、わしは永年人相見をやってきておって、人の性格、これからの運命、今まであゆんで来た人生、そして、今考えておることがわかるようになった」
「…そっ、そんなことがあるんですね」
「そうじゃ、世の中には不思議な事はいろいろあるもんじゃ。ちなみに、おまえさん、幸運を呼ぶお札を欲しくないかの?」
「幸運を呼ぶお札?!」
幸運という言葉に、T氏は誰よりも敏感であった。
「本当にそんなお札があるんですか、あるなら僕に譲ってください」
椅子から立ち上がり、老人につかみかかるかのごとく興奮したT氏。それをなだめるように老人は答えた。
「わしの手元には3枚だけ、残っている。譲ってもいいだが、お札だけになかなか融通の利かない部分もあっての。あまり過度な望みをかけると代償をとることもある」
「いや、いいんですよ。私の命さえ無事ならば、多少の損害は構いません。願望の達成の方が優先です」
必死に追い縋(すが)るT氏に、老人はいやしく低い声で笑った。
「ふほほほっ、おまえさんは願望達成の虜のようじゃの、では特別に譲ってやろう」
そう言うと懐から3枚の古ぼけたお札を取り出した。
こうしてT氏は長野で、奇妙な老人から願望が達成できるお札を購入したのだ。
それから、数年T氏はお札を温存していた。会社が危機に陥った時、使うために大切に保存していたのだ。
購入した時に、老人から聞いた話によるとお札を深夜、川や海にほうり込み願望を大声で口にするとよいのだという。
(俺にはこのお札がある。決して企業戦争に負けん)T氏は時々深夜に、お札を眺めると、一人で悦に入っていた。
しかし、会社のピンチはやってきた。石油ショックである。この突然の不況に彼の会社もあえぐことになった。
(いかん、このままではうちの会社はつぶれてしまう)
ある夜、関東の某県の海岸に立ったT氏はお札を海中に投げ入れると大声で願掛けをした。
「うちの会社を救ってくれ」
その後、T氏の企業に某大手企業が出資し、新たなプロジェクトも成功した。奇跡的に、T氏は不況を乗り越える事ができたのだ。
だが不幸な代償も要求された自分の兄弟が交通事故で亡くなってしまったのだ。
(すまん、すまない、私のせいだ、許してくれ)T氏は兄弟に心から詫び、号泣した。
その後も、バブル崩壊で2枚目のお札を使った。この時は、父親を亡くした。
(わっ、私はもはや鬼畜のような業をなしている。しかし、会社を守るためなんだ。どうか、許してくれ、親父)
残りのお札が一枚になった時の事。既に時代は平成の半ばとなっており、T氏も引退を考えていた。
(最後のお札はどうやら使わないですむようだ。よかった。よかった)
本社ビルから夜景を見ながらT氏はそう思った。既に会社は息子たちが中心に廻っており、自分はお飾り的な存在である。ようやく彼のビジネスライフも終わったのである。
しかし、運命は最後まで彼を翻弄した。突如、社員によるミスで会社に莫大な損害生じてしまったのだ。
(いかん、このままでは潰れてしまう)
T氏を久々の焦燥感が襲う。時計の秒針の音が妙に耳に響いてくる。社員たちが入れ替わり立ち替わり、会長室に報告してくる。
「どうしよう、おっ お父さんどうしましょう」
電話では、息子や娘婿が泣きついてくる。情けない声にT氏は余計に腹が立った。
(仕方ない、あの最後のお札を使おう)T氏がお札を取り出した時、携帯電話に一方が入った。
「会長、奥様が倒れました」
彼は呆然としてこの40年間、ずっとささえてきてくれた妻である。役員として会社の経営にも参加していた妻だったが、直属の部下が引き起こした今回の失態に心労が重なり倒れてしまったのであろう。
(いったい、どうすればいい?お札はもう一枚しかない)T氏は夕闇の迫る会長室でぼんやりと窓がながめた。
妻と共に働き、寝ないで大きくしてきた会社である。今は息子や、娘婿たちもおり、一家の大切な会社である。まして、おさない孫まで路頭に迷わすことはできない。
しかし、私にとって一番大切なものは妻であるはずだ。T氏は、運転手を呼ぶと役員会議を欠席し、ある海岸に向かった。過去2度、お札を沈めた海である。
そして、深夜まで待つと、海にむかってお札を投げ込んだ。
「私の妻の病気を治してください」
夜の海に彼の声が響いた。
翌日、T氏は意識が戻った妻と病室にいた。会社は引責辞任という形にして退いたが、その事件以後は、大幅に経営規模を小さく
せざるえなかった。それでもどうにか会社は存続することができた。
T氏はこう言った。
「あのお札は、成功を与えると同時に代償を求める悪魔なんです。だから、もし3枚目も会社のために使っていたら、妻どころか、僕の命もなかったのかもしれません。本当の幸せは妻との生活にあるんです。お札は本物の幸福を教えてくれました」
ごく普通の男に戻ったT氏の笑顔はさわやかであった。
幸福への執着は時に、真の幸福を見誤らせる。
(山口敏太郎 ミステリーニュースステーション・アトラス編集部)
画像©写真素材足成