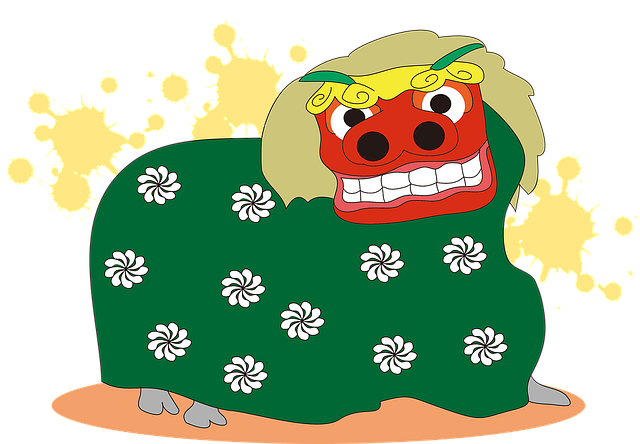近代日本における怪談を流布した功労者といえば小泉八雲、その人であろう。日本に帰化する前の旧名は、パトリック・ラフカディオ・ハーンといい、ギリシア・レフカダ島にて生を受けた。
なおハーンという姓は、ジプシーの出自であり、ハーンの叔母にあたる人物が、アイルランドの田舎道でジプシーに未来を占ってもらったところ、「あなたは私たちの仲間です」と言われたというエピソードと玄孫である小泉凡氏が「民俗学者小泉八雲」(恒文社)にて紹介している。八雲本人もジプシーの血統である事に誇りを持っていたらしいが、ついに最後まで定住しなかった彼の生き様の本質はそこにあるのかもしれない。
アイルランド人の父親と、ギリシア人の母親との間に生れた八雲は、アイルランドのダブリンに移住するが、両親の離婚により、近在に住む大叔母に引き取られる事になった。
この後、八雲は多感な少年時代を大叔母のもとで過ごす、16歳のときに左目を失明し、父を病気で失っている。更に、資産家であった大叔母の破産により退学に追い込まれてしまう。この当時、八雲は霊や妖精等、怪しいモノを目撃する体験をしている。これら少年時代に巻き込まれた神秘体験が後の名作「怪談」に影響を与えたのは言うまでもない。
その後、19歳でアメリカへ渡り、職業を転々としながら24歳のとき新聞記者となる。数々のスクープをものにし、明治23年(1890年)雑誌の特派員として念願の来日を果たす。この八雲の新聞記者時代、記事20点が最近発見された。当時八雲は、米国地方新聞の「シンシナティ・インクワイアラー紙」と「シンシナティ・コマーシャル紙」に記事二十点を寄稿している。期間は1874年3月から76年9月までに該当しており、小泉八雲の研究家・檜山茂氏が、米国オハイオ州シンシナティ市にて発見した。
驚くべき事に、1875年12月9日付のコマーシャル紙の記事で、八雲記者は幽霊に触れている。不審者が民家に侵入した事件の報道記事で、夫が犯人を追いかけたものの、妻の寝室から幽霊のように忽然と衣服だけを残して消えたというくだりである。ことの真相は妻の間男を幽霊のように消えたと、誤解した夫の茶番劇だったが、この時、既にハーンが「幽霊」というものに対して興味をもっていた証拠である。
その後松江中学に英語教師として赴任し、熊本の五高の教師を経て、東京帝国大学で英文学について教鞭をとった。この当時、八雲の講義は学生たちに圧倒的な支持を得ていたという。八雲が退任し違う英語教師が来るとわかった時は、学生たちは激怒し、八雲の留任を求めて抗議運動をしたという。因みに、八雲の後任英語教師は、あの夏目漱石であった。
日本で八雲は初めは「ヘルンさん」と呼ばれていたが、これは松江の島根県立中学校への赴任辞令に、「Hearn」を「ヘルン」とローマ字読みで表記したのがきっかけであり、本人もこの愛称をいたく気に入っていたという。なお八雲の周辺では、八雲と家族、使用人、書生など親しい人たちにだけ通じる「ヘルン語」という日本語と英語の混じった言葉があったらしい。
このエピソードなども、八雲の人柄を伺わせるものである。また、ハーンの日本名である「八雲(やぐも)」は、居住地である島根県・松江市の旧国名である出雲国にかかる枕詞の「八雲立つ」にちなむとされてきたが、「八雲を音読みにするとハウンになる、つまりHearn」という仮説も唱えられている。
八雲は、『日本瞥見記』『東の国から』などの随筆集での評価も高いが、「耳なし芳一」「むじな」「雪女」など怪談作品でその評価を絶対なものにしている。かつてこの八雲は、大叔母ブレナンの家に、秋から春にかけて逗留するジェーンという女性の生霊らしきものを目撃しており、その顔がのっぺらぼうであったと回想している。怪談「むじな」への布石は既に打たれていたのだ。
関連動画
virtual trip 出雲・松江 日本の面影 プロモクリップ
(山口敏太郎 ミステリーニュースステーション・アトラス編集部)